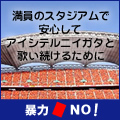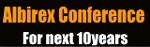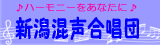現実に行われている「戦争」を「公共事業」に喩える場合がある。
軍事産業への多額な公共投資とか、兵士という大量の雇用創出とか、あるいは大規模な破壊行為の後に生まれる復興事業、というような側面をみれば、そういう喩えも成り立つだろう。
しかし、それが比喩ではなく、本当に「公共事業」の一つとして「戦争」が行われるとしたら?
しかも、その戦争の相手が「となり町」だとしたら?
月2回配布される町の広報紙の片隅で「となり町との戦争のお知らせ」として開戦が知らされる。
まるで下水道工事の地元説明会のように、戦闘地域に該当する町内会で説明会が行われる。
このあたりのお役所仕事の描き方が、細部にわたってあまりにリアルだったので、公務員経験者でもなければこうは書けまい、と思った。
読み終えた翌日に開いた新潟日報に、著者が写真入りで紹介されていた。
職業は、やはり思った通り、市役所の職員だという。
「亜記」っていう名前から女性だと思っていたのに、男性だった。
ここで展開される「戦争」は、私たちが普通に思い浮かべるものとは様相を異にする。
なにせ公共事業なので、コンサルティング会社やら請負業者やらが暗躍するw
パロディ、のようでもあるけど、筒井康隆ほどではない。不条理、なんだけど、カフカほどでもない。
「ほどほど」なところがちょっと物足りないけど、発想のおもしろさと淡々とした文体で一気に読める。
小説すばる新人賞受賞作。
となり町戦争
三崎 亜記