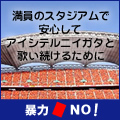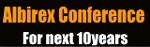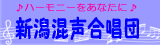今回の東日本大震災と、2004年の新潟県中越大震災と。
あまりに違うので、気づいたこと・調べたことを書き留めておきます。
どちらの地震も最大震度は「震度7」。
中越地震では新潟県川口町が、東日本大震災では宮城県栗原市が、
それぞれ震度7を記録しました。
で、その被害は?
とりあえず、建物の被害だけで比較して見ます。
【新潟県川口町】
○2004.10.1現在
人口 5,530人
世帯数 1,595世帯
○地震による建物被害
全壊 339棟
大規模損壊 74棟
半壊 223棟
一部損壊 111棟
【宮城県栗原市】
○2011.2.1現在
人口 74,558人
世帯数 24,614世帯
○地震による建物被害
全壊 5棟
半壊 16棟
一部損壊 138棟
宮城県栗原市の建物被害が、びっくりするほど少ないです。
同じ「震度7」でありながら、これほど住宅被害に差があるのはなぜ?
直下型の地震と、海底が震源だった地震の差でしょうか?
いわゆる「キラーパルス」が発生しなかったのでしょうか?
宮城県では、3年前の2008年6月に「岩手・宮城内陸地震」を経験していて、
そのときの栗原市の震度は「震度6強」(この地震の最大震度)でした。
もしかしたら、地震で倒壊するような建物はこの時に倒壊してしまったのかな?
とも思ったのですが、この地震でも「キラーパルス」が発生せず、
震度の割には建物被害が少なかったようです。
「震度7」と聞いた時に、
山が崩れ、住宅が潰れ、路面が割れてめくれあがっている、
あの中越地震の光景を頭に思い浮かべた私でしたが、
実際に行ってみて、全く違う、と思いました。
石巻市(人口160,336人・60,905世帯)では、全壊が約28,000棟、
半壊・一部損壊は「調査中」となってます。
仙台市も建物被害は「調査中」となっていて、全容が分かりません。
今回の地震の被害のほとんどが、津波による被害だということが理解されます。